信仰の再解釈と美的反映について–
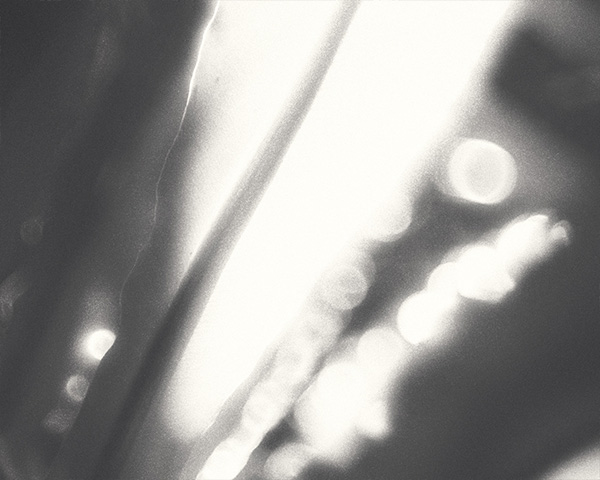
信仰の再解釈と美的反映について
瑚山朋令
かつて祭祀は非日常空間において共同体としての役割を負う抑圧された個別性の開放と、儀礼による身体的了解の二重性によって機能していた。科学技術と経済活動によって社会は自由競争化し、自然はコントロールされ、合理化追求の果てに風土はどのように変容するのか。
個別性を獲得し生きることが容易になった今、即時的な効果が見込めず生活を縛り付ける祭祀は忌避されつつある。ここで現代における宗教的儀礼の再解釈と精神的活動の所在の弁証法的相互作用がいかにあるべきかを改めて理解しておく必要がある。
廣松渉によると戒律や儀礼のようなものは共同主観であり、それは「〜としての私」という構造によって伝達、維持されているという。所与、つまりその場に与えられた既成の事実、以上の記号を「地域に属している人間としての私」が理想的に振る舞うことによって次々と作り出し、そして集合表象を形成するのである。
地域における風習が予めその土地の発生と共にあったかのように認識させ、秩序として存続させている機能がこれにあたる。
また信仰を支えているのは「〜として」の分人的活動だけでなく、日々の日常的に行われる信仰儀礼である。儀礼とはそれ自体は無意味であり、それはそういうものである、というトートロジーの形象である。根拠の原理をどこかでストップさせる無根拠の肯定である。
これはすべての事実の前に「私」が存在しているという身体の原理と等しい。体を使う儀礼というのはそこに唯一無二である身体がわざわざ向かうことで、この一回性=「ここで現前するものと唯一の身体との出会い」を有意味的に自分に納得させることになる。これは時間が有限であることを認識できる人間の思考傾向でもある。
しかし信仰や宗教は近代化により儀礼や道徳を放棄していく。無根拠を肯定するためのまつわる諸要素が剥がされていき、最低限の儀礼のみで身体的了解を得るように変化する。ここで最も重要なのが、信仰の本質が「こうするべき」という道徳的諸要素ではないということである。
宗教が原理の追求を切断し、合理化できないものを受容するシステムであるからこそ、「こうするべき」から最も距離を置くべきなのである。戒律や儀礼を重んじていた祭祀が現代において再解釈される余地がここに存在する。
では、想像上の秩序による呪縛を回避しつつ、人間存在の豊かな精神性と社会的規律を両立させるにはどうしたら良いのか。
現代における身体性をともなった儀礼的制度といえば、それはディシプリンであり、人類が歴史的経験のもと紡ぎあげてきたあらゆる暗黙のフォーマットである。フォーマット、行動の事前了解や媒体の制限こそが果てしなく続く社会の意味追求を切断し、次なるアクションへと駆り立てる。
そしてその人間と社会の諸関係の変動は人の日常的活動に基づいている。ではこの日常的活動の源流、人類の精神的発展に直接的に寄与しその客観性を持って強固に固着させる形象を生むものは何だろう。
ルカーチは美的反映という概念において次のように言う。日常において限定されたフォーマット上で行われ儀礼的でもある芸術行為は日常の主体へ直接的に喚起し、より高い客観性を持った作品によって脱却した日常との相互作用が生まれるのだ、と。つまり「芸術」、ここでは広義での「表現」と言い換えても良いが、何らかの術を持って表すことが、身体性を通した肯定、変貌、揺らぎを儀礼的フォーマットに乗せて、日常の主体と外化された作品のあいだを行き来することになるのである。ここには自由な精神の向上と社会的自律の上向きベクトルが発生している。
ルカーチはこの相互の作用=美的反映をアリストテレスのミメーシスという概念を用いる。
身体性を通して世界のあり方を模倣(ミメーシス)することが、永遠の合理性追求とは別の仕方で、この理解し切れない世界を受容できる方法なのではないか。それは形骸化する信仰よりも具体的に人間に作用し、根拠の有無を問わないメタフィジカルな豊かな代替秩序なのではないかと私は考える。
別の論考では御嶽の空性について着目した。空は即の理論であり、何かに転じることのできる自由を持っている。
宮古において信仰によって培われた風土は残っている。しかし信仰の儀礼は減少し続けている。
この失われた「無根拠を肯定するもの」を、美的反映の繰り返しの中に見る「人間の善を希求する力」に求めても良いのではないだろうか、というのがここでの一番の趣旨である。それらの美的反映=表現、芸術が、個人の暴力的とも言える欲求の代替物であったりアテンション・エコノミーに利用されない限りにおいて、死者や神という非物質の意向中心ではなく、今生きている人間中心の豊かな精神性へとまた還元されるのである。
かつての信仰は超越的なもの、到達できない彼岸の中に人の希望を収斂させ人間の独自性を萎縮させてきた。表現、ひいては芸術は、人間の現世的生活が持つそれ自体において意味があること=身体のトートロジーを自らの手によって肯定するサイクルなのである。
御嶽における精神性と意義の変遷について–

御嶽における精神性と意義の変遷について
瑚山朋令
御嶽とは恣意的な決定を回避し権力者による強制的統制にも反して、絶対的他者(自然の脅威や不可知な神的存在)による選択を半ば受動的に享受することにより民意の中和を試みるものである。御嶽の目的とは、社会秩序を維持して大規模な協力体制を組織するための同時代的手段としてであった。
かつて情報化以前の地域社会においては、統制手段が人間以上の優位によるもの、つまり予め確定された「そういうもの」による能動的了解を得ることこそが非常に重要であった。というのも徹底した制度と認識の合理化がもたらされる以前においては、こうした集合意識の遅延——理性的判断を先伸ばしすることで、やがて向こうからやってくる自然現象や外的要因が「意味あるもの」として付与されることが世界の理解に不可欠だったからである。
ここで重要なのは人間の個別精神と神という絶対的実在との関係性である。ヘーゲルによると信仰者は禁欲的生活や儀式を通して個別的自己を犠牲にして、その地域が持つ共同体の共同精神、いわゆる普遍的精神に同一化しようとする。これは祀られる神が自己犠牲的な地域の功労者であったりすることと無関係ではない。つまり祖霊と神という存在規定の曖昧さからも、神は彼岸にあらず人と同一であることの事実性を公にしないまま表象として指し示すという構造がここにある。そしてキリスト教のような啓示宗教における人間の形での自己意識の語りを得るには代弁者が必要であるが、島の信仰においてそれは神司の役割となっている。
しかしここには第一段階としての自由意志が存在しない。エーリッヒ・フロムがいうように「自由」は、何者かに従属したいという基本的欲求を備えた人間が自ら手放してしまうものである。そして選択可能性の不安定さを受け止め、個として意図的に独立を望んだものだけに備わるものである。
そして第二段階としての自由意志も存在するか定かではない。ユヴァル・ノア・ハラリが指摘するように人は生命科学的アルゴリズム上でただ反応しているだけである、と言えなくもない。
しかしこれは両極端な話ではあるので、もう少しこの中間点について解像度を上げる必要がある。
御嶽の形式に話を戻すと、御嶽は本土における伊勢のような、純化する形式の内に神聖を見出す構造が存在しない。伊勢においては、簡素な、物事の骨子となる基本構成要素と意味解釈的物質を複合したもの=本質によって何らかの具象形状を認知させ、崇高な対象として表意させる。そういった聖なるもの、「白」の情報量は、無数に何かが生まれ出る兆しを認め、時折形を持ち、そして生まれ変わる。御嶽においてこのような感覚を予期し含むものとしての形式は、白という純化のフィールドではなく、そもそも何も存在しないこと=「空性」を帯びる形で存在している。つまり神の所在を認知させるために「側」が崇高であること——人間のスケールを大きく超えたものとして量的質的に人為を尽くすのではなく、あくまで崇高なものが自然それ自体であるかのように、森の中心空間そのものを聖域としている。
社殿等によって永遠なる中心を囲うことで神聖を保つのではなく、もともとある森や木の袂に中心を見出して、無為にその状態を良しとすること、「白」く清浄に洗練させるのではなく、無為自然の関係性の調和を体現していることが御嶽の形式には見て取れる。私は最初に宮古に「無何有」を見て訪れた。無何有とは無作為で、あるがままの自然状態を表す言葉であるが、その景色のもとを辿ればそれは御嶽そのものであった。
ここに「透明」なる御嶽の真髄があると考える。透明であること=transparentは、通り抜け、現れるという由来があるが、「物体が光を通すこと」を意味する。御嶽は大抵薄暗い森の中にあり、日中であれば木々の合間から光が見える。宮古では日々強烈な太陽光が降り注ぐがこれをあえて遮断させ暗がりで仰ぎ見ると、当たり前のように世界を照らしていた太陽が、改めてひとつの存在として目の前に現れ視認できる。光がすでにあったこと、それを自覚できる場所、そこが御嶽という場であり、万物の源=ムトゥと言われるのにも納得がいく。
この透明で「すでにあった」光を再認識することで、意識拡張や選択、認識変化などを経て何も無い空間は有へ転ずるのである。つまり無即有、無から有を見出す行為がここにある。
宮古では人は死してオーミュウへ向かうという。青は死者を繋ぎ、紺碧の大海から白波が打ち寄せるように再生の白へと変ずる。宮古は「現世」を意味するが、その根の部分——地底や海底は「常世」となり、この常世=ニッジャを通じて時折、神の使いはガー(泉)から現れるという。こういった現世と常世を巡る円環的循環の中に人は時間的安定性と死生観の形成をし、その核として御嶽を設置した。この御嶽が自然によって形成されたわずかな空間、例えば手のひらをあわせて包むようにすれば手のひらという面からわずかな3次元の椀が生まれるように、次元転換の空間認識によって無に文脈を付与し、生の根源的価値を肯定するかのような有の発露——空をここに垣間見るのである。
